ASDタイプの子どもをサポートする上で、親の重要ミッションは2つあると思っています。
2つのミッションのうち、今回は その1 について綴ります。
その1 ASDタイプの子を独りで戦わせないこと ~外の世界にも理解者をつくる~
その2 親がASDタイプの子に合った接し方ができる自分に進化すること
今回は、なぜASDタイプの子を独りで戦わせないことを親のミッションと捉えているかをお話します。最後に我が家の取り組みについてもご紹介します。
ページ1
●ASDタイプをサポートする上でのミッションというテーマを取り上げた理由
●わたし自身はどのようにして特性に気付いたか?の話
【例】息子とのあるある
ページ2
●特性を見過ごされている(のであろう)子の話
【落とし穴?】できたママほど、我が子のASD特性に気づくのが難しい?!
ページ3
●ASDタイプために “家庭外の環境を調整する” 必要性について
●社会とフレンドリーであることの重要性について
【実例】独りで戦わせないための我が家の「環境調整」
ASDタイプをサポートする上でのミッションというテーマを取り上げた理由
最近、つくづく思うのは、
わたしの接し方さえ悪くなければ、息子の特性が原因で問題が生じることなんて、ほぼないんだよな…
ということです。
彼が障がいを持っているのではなく、わたしが障害物になってしまっているのだ。
それを噛みしめることが多いのですが、そんな折、ふと思ったことがありました。
わたしのような子育てが下手くそな母だと特性があることにすぐ気付くけど、大らかで寛容なお母さんだったら特性に気付きにくいかもしれないな…と。
その時、あるお子さんのことを思い出していたのです。
今思うと、あの子は、特性を見過ごされてしまって、つらい思いをしている子…つまり独りきりで戦っていたのではなかろうかと。
この記事を書いたのは、その子のように、孤立無援で必死に頑張っている子が実は多い気がしてならなかったからです。何と戦っているのかすら分からないままに。
我が子じゃないにしても、そんなつらいことはあってほしくない、そんなつらいことはなくなってほしいと願い、今回のテーマを取り上げようと思い立ちました。
本題に入りたいと思いますが、そういう子のお話をする前に、話の整理のために、まずは我が家の例からお話ししていきます。
わたし自身はどのようにして特性に気付いたか?
まず、先ほどの子の話で、特性が見過ごされている可能性について触れました。
では、我が家の場合は、どのようにして特性に気付いたのか?
わたしが特性を知ることは容易いことでした。なぜなら、特性による困り事が表出しやすい環境をわたしが自らつくり出していたからです。
前述のとおり、わたしが障害物になっていたので、障がい(困り事)が頻発していたということです。
では、なぜ優れた母でないと特性がわかりやすいのか?
ASDタイプにとって好ましくない “優れていない母” とはどんなもので、どんな困難に直面するのか?をわたしの例でご説明します。
わたしは学生時代(昭和)、ずっと運動部に所属していたような人物です。つまり、THE体育会系マインドを持った人間です。
例えば、自ら考えて行動するよう含みを持たせた指示をしたり、体育会系ノリで発奮させるようなキツめな言い方をしたりしがちなのです。
これはASDタイプの子には適さない接し方で、そのミスマッチから、分かりやすく負の反応が戻ってきます。
【わたし】自ら考えて行動するよう含みを持たせた指示を与える
↓
【息子】ASDタイプは含みを理解するのは困難(=わたしの指示が悪い)なので、何をすればよいのか分からず、やりたくてもやれない(息子からすると指示者に落ち度があるという感覚)。なぜそんな指示の仕方をするのか憤る。
↓
【わたし】態度が悪い!大人をなめているのか?!
(含みのある指示でも、こちらの感覚で)分からないわけはないと思い込み、やれるのになぜやらない?!と怒りを覚える。
↓
【息子】(指示者が悪いのに)叱られることが不本意なのでキレる。
↓
【わたし】いちいち、なぜ反抗するんだろう?
【わたし】発奮させるようなキツめな言い方で指示を与える。
↓
【息子】親子という関係性を踏まえた(=親は敬うものという感覚はない)言動をすることができないため、親(養育者)であろうと全力で歯向かいます。
↓
【わたし】なぜこんなにも反抗的なんだろう?
普段は穏やかで愛嬌のあるタイプなので、そのギャップがあまりに大きすぎて、いつも驚かされていました。
これは、わたしの接し方が、ASDタイプにとって好ましくないものだったゆえに起こったマイナス事象です。穏やかに、具体的に、丁寧に指示を出せば、こんなことは起こりません。
ASD特性への理解が進むほど痛感したのは、
やはり問題が生じるのは、こちらの接し方がよろしくない場面
だということでした。

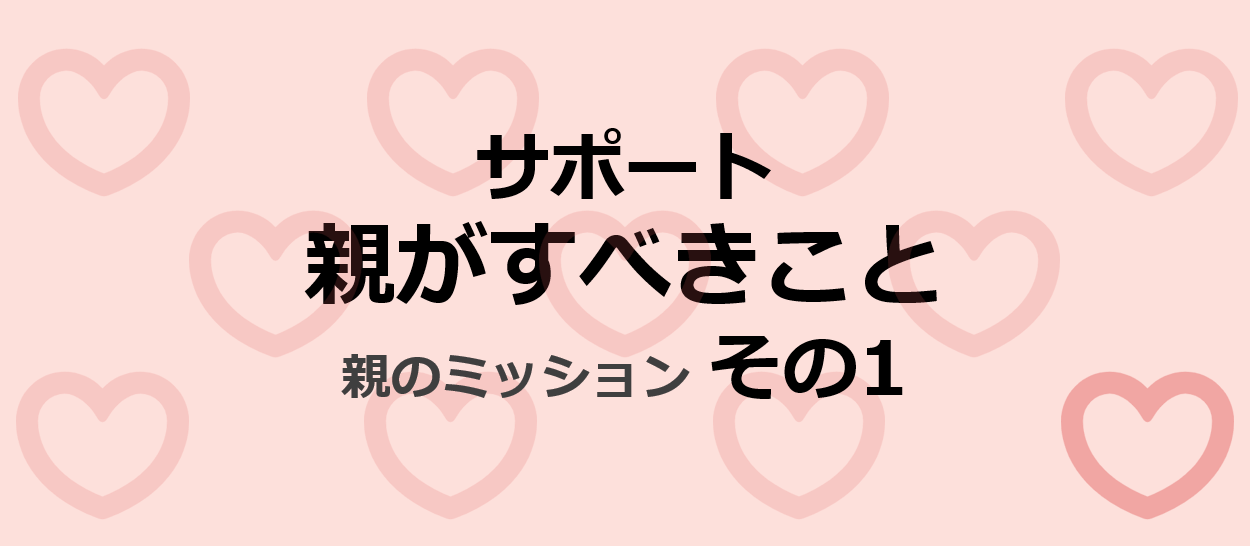
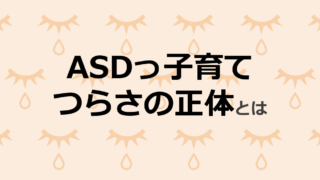
これまでの子育ての学びや気付きをこのブログでご紹介することで、同じ境遇の方のお役に立てたらうれしいです。